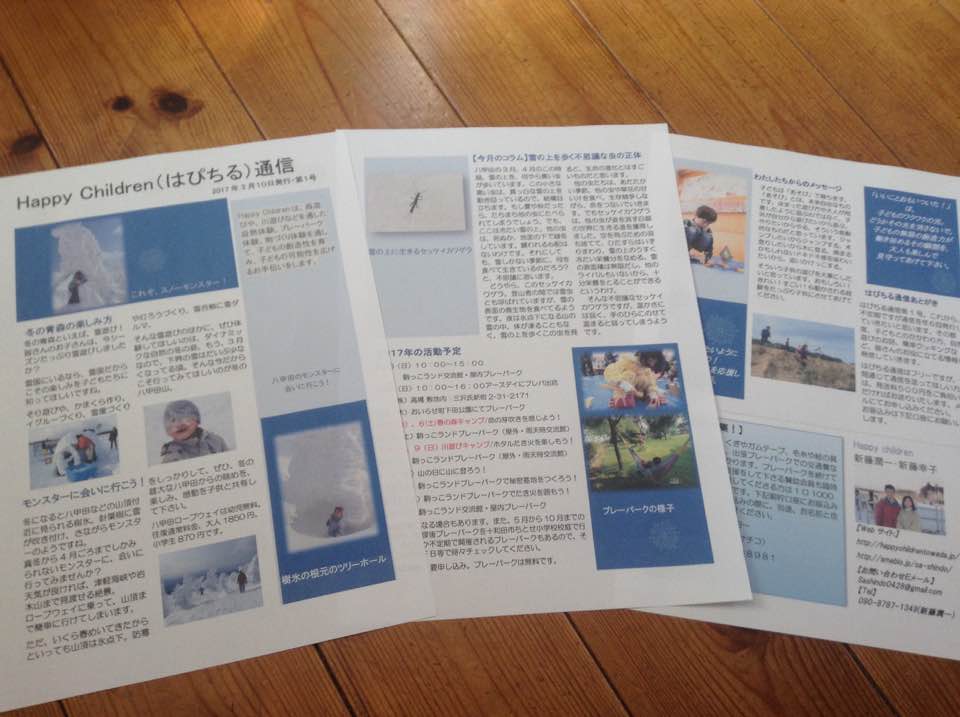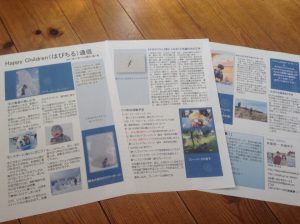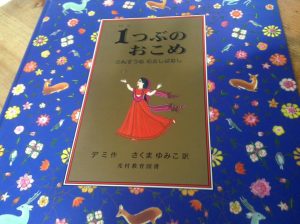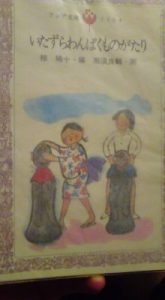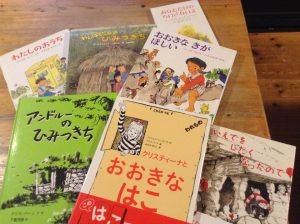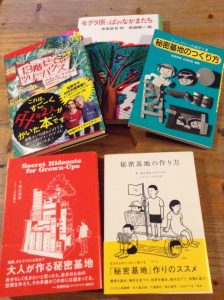親であるなら誰しも、子供が幸せに育ってほしいと願っているものです。では、子供の幸せって、何でしょう?どんな大人になってもらいたいですか?
健康であること。人に必要とされる人であってほしい。幸せな家庭を持ってほしい。食べることに困らないように。お金の苦労をしなくていいように。いろいろあると思います。
でも、究極は、子供が幸せを感じて生きてくれれば、それでいいのではないでしょうか?
その、幸せを感じる心は、自己肯定感が大きく関係しています。
皆さんは今、幸せですか?皆さんのお父さんやお母さんが願ったように、「私は今とても幸せです。」言えるでしょうか?お互いのご両親がいたからこそ生まれてきて、出会い、結婚し、子供に恵まれ、そして、毎日を楽しく生きている。だからこそ、ご両親に産んでくれてありがとうと言えるでしょうか?
そして、もう一つ質問。皆さんは、自分のことがどのぐらい好きですか?
幸せは自分の中にある
以前、ドリームマップという夢を描き出すという講座に出たときに、ある質問をされました。
「あなたは、自分のことがどれぐらい好きですか?」と。
紙には空のコップの絵が描いてあって、自分の好きさを水の量で表してと。たくさん好きな人は、コップにいっぱい満たされた水を描き、自分のこと少ししか好きじゃないという人はちょっとの水、というように。
その時、大人20人ほどいた参加者の中で、水を一体満たしたのは二人。八分目ぐらいの人が数人と、後の人は半分ぐらいが多かったように思います。
これが、中学校で同じ質問をすると、コップに水がほとんどないという子も結構な割合いて、いっぱいという子はほとんどなくて、多くて八分目、ほとんどは半分ぐらい。
自分をあまり好きではないという子が、とても多くてびっくりしたことがあります。
自分を好きっていうのは、自己肯定感そのものです。
そして、何をもって幸せを感じるかは人それぞれです。何不自由ないお金があれば幸せ。おいしいものが食べられたら幸せ。家族みんなが健康であれば幸せ。家があるから幸せ。子どもがいるから幸せ。自由に自分のことができるから幸せ。人のお役に立てて幸せ・・・。
でも実は、絶対的に、これだから幸せっていう定義はないですよね。
その定義は、人それぞれで違うものだし、今日朝日がすごくきれいで、すがすがしい朝だったから幸せって感じる人もいれば、たくさんいろんなものに囲まれて、それでもまだ、いい車もほしい、持ち家もほしい。自分のやりたいことができずに、日々のちょっとしたことに幸せを感じることができない人もいます。
幸せを感じる心は、ただ一つ。自分を幸せにしてるかどうか。自分を大切に思っているかどうか。自分のことが好きかどうかです。
自分を大切にしている人は、空が青く澄んでて気持ちがいいとか、鳥の鳴き声や、吹き抜けるさわやかな風にすら幸せを感じられるものです。朝、一杯のコーヒーを飲むという行為だけでも幸せを感じるものです。
でも、自分を大切にできていないときは、あれがないから幸せになれないんだ、これがないから幸せじゃないんだ。あれさえあれば幸せなのにと、ないものばかりを求めるものです。
やはり、子供たちには、日々幸せっを感じてほしいものですよね。
では、子供が、自分を大切にして、日々幸せを感じて生きて行ってもらうために、私たち大人は、どんなことができるでしょうか?
自己肯定感の低い子供たち
今、日本の子供たちの自己肯定感の低さがいろんなところで問題になっています。海外に比べて、かなり低いのです。
日本を含めた7カ国の満13~29歳の若者を対象とした意識調査で、自分自身に満足しているという若者は、アメリカが86%、フランスが82.7%に対し、日本は45.8%。
うまくいくかわからないことに取り組める意欲があるのは、フランスで86.1%、アメリカは79.3%、日本は52.2%。
将来に希望を持っているか?という項目では、アメリカ91.1%、フランス83.3%、日本61.6%です。
どうやら、自分に満足感が得られないと、将来に希望を持ったり、うまくいくかわからないことにチャレンジする意欲が持てないということになりそうです。
では、その、自己肯定感の低さはどこから来てるのでしょうか?この調査では13歳から29歳の若者に対して行われています。ということは、小学校卒業までに、そういう子供たちができてしまっているということです。
その要因として考えられているのは、家庭の中においては、あれをしなさい、これをしなさい、早くしなさいと、指示を送り続けていること。以前の記事で、指示待ちの子供たちの記事にも書きました。自分で考えてやってみるという経験が少なくなっているとのではないかと思うのです。そして、やってみて、失敗して、その失敗から学ぶ経験が少ないということ。失敗したら笑われた。失敗したら、だから言ったでしょと怒られる。チャレンジして失敗して恥をかくより、失敗しないようにチャレンジしないという道を選択してきた子供たちが大きくなってきているのだということ。
そして、親の愛情というのも言われています。愛情といっても、ただかわいがっていればいいということではなく、子供を信頼しているか?ということです。失敗しても、あなたなら大丈夫。きっとできると見守れるというのは、子供を信頼していなければできないことです。
信頼するって、簡単なようでいて、意外と難しいものです。失敗するかもしれないのを手を出さずに見守るというのは、忍耐が必要です。ついつい手や口が出てしまいます。
自己肯定感は、大事にされること、信頼されること、失敗してもチャレンジする経験の繰返しで少しずつ積み重ねられることで育まれていきます。
親やおじいちゃんおばあちゃん、周りから大事にされる存在だという承認があって、初めて自分が大事にできるようになるものです。
大人も自分自信を大切にしよう
大人でも、この自己肯定感を持てない人が多くいます。それも、今までの経験の中で、失敗したら笑われたとか、何やってるんだと怒られたりという経験の中でできあがっていったもの。でも、それなら、自分で自分を大切にしてあげるところから始めてみたらいいんじゃないかと思うんです。
まあるい抱っこの時も辻直美先生から、自分を抱っこするのよと、お話がありました。まずは自分を大事にするんだよと。
時には、育児のつらさから、自分なんて、母親失格だとか、何にもできていない自分にダメ出しばっかりしてしまうときもあるでしょう。でも、そんなときこそ、自分を優しく包み込んで、自分を大事にしてあげてほしいんです。自分はよくやってると、自分で自分にご褒美をあげてほしい。自分を大切にできるようになれば、子供がかわいく思えてくるものです。
自分を大切にするというのは、大人にも必要なことで、具体的なデータはないのだけれど、自分を大切にできる親に育てられてる子どもは、自己肯定感も高いのではないかと思っています。
どうしても自分が好きになれないとき、でも、そういう感情もまた自分自身なのだと、いったん受け止める必要もあるかもしれません。自分のどこが好きじゃないんだろう?自分はどうなったらいいと思うんだろう?客観的に、自分を高いところから俯瞰するように、自分を見つめてみる必要もあるかもしれません。
どんな人も、感情に浮き沈みはあるものです。いい感情も悪い感情もなく、ネガティブな感情も、とことん落ち込んで浮上するためには必要な感情のこともあります。そこが次への原動力になることもあります。
どんな自分もオッケーと、まずは、自分を抱きしめてみましょう。